EA開発で単純な移動平均線のクロスでのシャープレシオ:0.38からシャープレシオ:1.57に改善した例がありました。
単純な移動平均線のクロスでも改善するという例ですが、裁量トレードにも利用できますね。
その全てを記載する事は出来ませんが、最近の自分の例で挙げると強烈なトレンドフィルターさえ出来てしまえばサインの精度はさほど必要ない。
実際に公開しているフィルターは種類で言えば3つありますが、未公開のもので言うと7つあります。
そして、今回の海外の事例から研究を始めたのが線形回帰スロープです。
線形回帰スロープ(LRSlope)とは
一定本数の終値に対して最小二乗法の直線を当て、その傾き(slope)を数値化した指標。
0より大きい=上向きトレンドの圧力、0より小さい=下向きトレンドの圧力。絶対値が大きいほどトレンド強度が強い。
仕様の要点
入力パワー: 期間中のN冊(例:50 冊)
出力:傾きのみ(0ライン基準)
時系列は「0=最新」。最新側の傾きが常に更新される
値は価格スケール依存。銘柄や桁が違えば絶対値の比較は不可。相対変化で見る
あらすじ
トレンドの方向と強度を一目で把握するための数値化ツール。
価格のノイズを平均化し、短期的な騙しに左右されにくい。
0ラインを境に強気・弱気の圧力を切り分ける。
メリット
方向判定が明確
0より上=上昇圧力、0より下=下落圧力。裁量の揺れを減らす。
強度を比較できる
絶対値の拡大=加速。縮小=減速。トレンドの勢い変化を早く捉える。
時間軸に依存しないロジック
期間Nの選定で短期~中期に自在対応。MAより応答が素直になりやすい。
視覚ノイズが少ない
ライン一本と0レベルのみ。判断が速い。
デメリット
価格スケール依存
銘柄や小数桁で傾きの絶対値は変わる。銘柄間の生値比較は不可。
レンジでのダマシ
ボラが薄いと0付近で頻繁に反転。フィルター併用が必要。
期間設定の感度トレードオフ
短いとノイズに敏感、長いと反応が遅い。用途に合わせて固定すべき。
水準の“過熱”基準は自作が必要
RSIのような汎用上限下限がない。過去分布から統計的に決めるのが妥当。
重要テーマ:価格が上がっているのにスロープが下がる意味
いわゆる陰のダイバージェンス(弱気の勢い低下)。価格は高値更新しているが、直近N本の回帰直線の傾きが低下またはマイナス化している状態。
なぜ起きるか(メカニズム)
期間窓の中身が古い強い上げから**新しい弱い上げ(または押し戻し)**に置き換わると、最小二乗の傾きが小さくなる。
新高値は出ていても、平均的な上昇速度が落ちているため、回帰直線の傾きは低下する。
解釈と使い方
トレンド減速の初期サイン
価格の見かけの強さと内部モメンタムの不一致。利食いの検討や新規順張りの慎重化。
0ライン接近の監視
上昇中にスロープが0へ収束=上昇圧力の消失。0割れで弱気優位へ遷移。
傾きの天井・山の切り下げ
価格は高値更新なのに、スロープの山が切り下がる連続性は弱気示唆の信頼度を上げる。
具体例(判定ルールの雛形)
価格が直近高値更新
同期間のLRSlopeが直近ピーク比で明確に低下、または0ラインへ収束
次の足でLRSlopeが前値比でさらに低下したら弱気バイアス強化
※実エントリーは価格アクション(前安値割れ、戻り売りの形)で同期させる。
実務的パラメータ運用
デイトレ短期:N=20~40
スイング中期:N=50~100
同一銘柄・同一時間軸で固定し、推移の相対変化を見る。
0レベルを初期表示。色は白、点線、太さ1で可視性を確保。
併用の基本
ボラティリティ指標(ATR等):減速とボラ縮小の同時確認で判定精度向上。
価格アクション:0割れ直後の戻り売り/押し目買いの形で実行。
マルチタイムフレーム:上位足のLRSlopeと方向整合を取る。
まとめ
LRSlopeは「方向」と「勢い」を数値化する基準線。
価格が上がってもスロープ低下は平均上昇速度の鈍化=内部弱化。
0ラインを軸に加速・減速を判定し、価格アクションで執行する。
絶対値ではなく推移と転換で読むことが最大のコツ。
おすすめ度 ☆☆☆
ダウンロードはこちらから



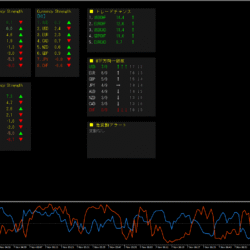


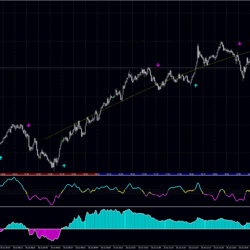
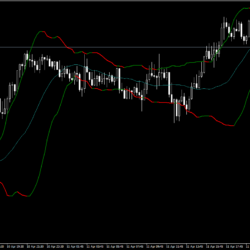


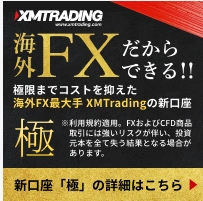

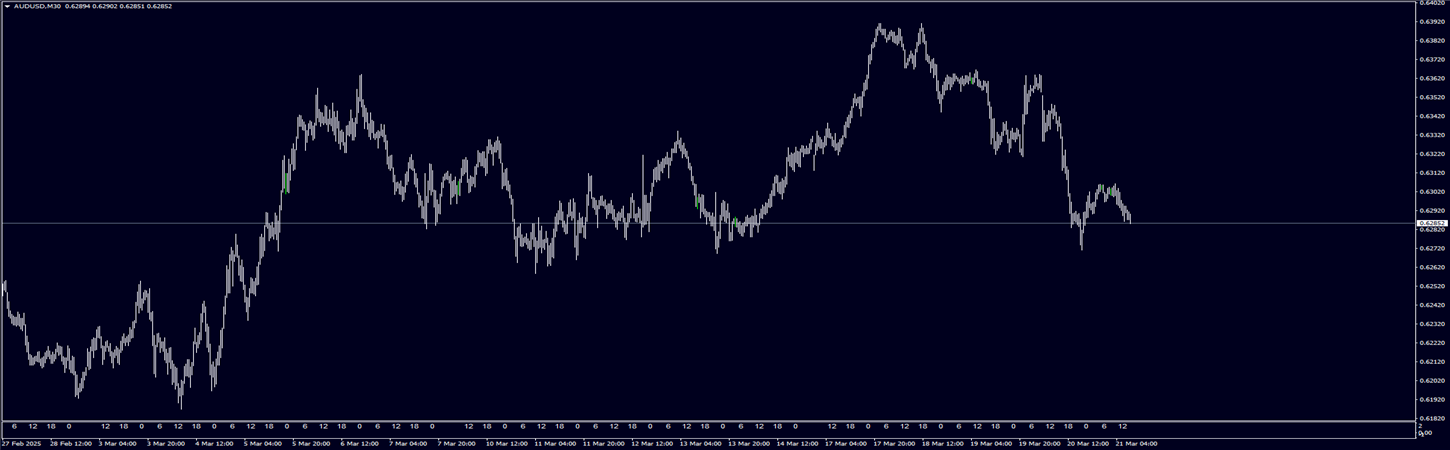
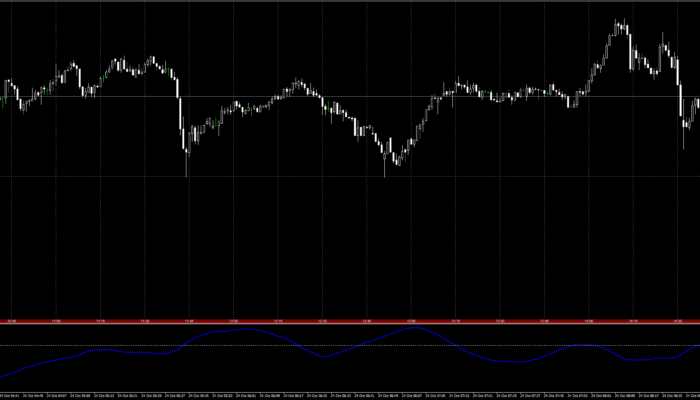
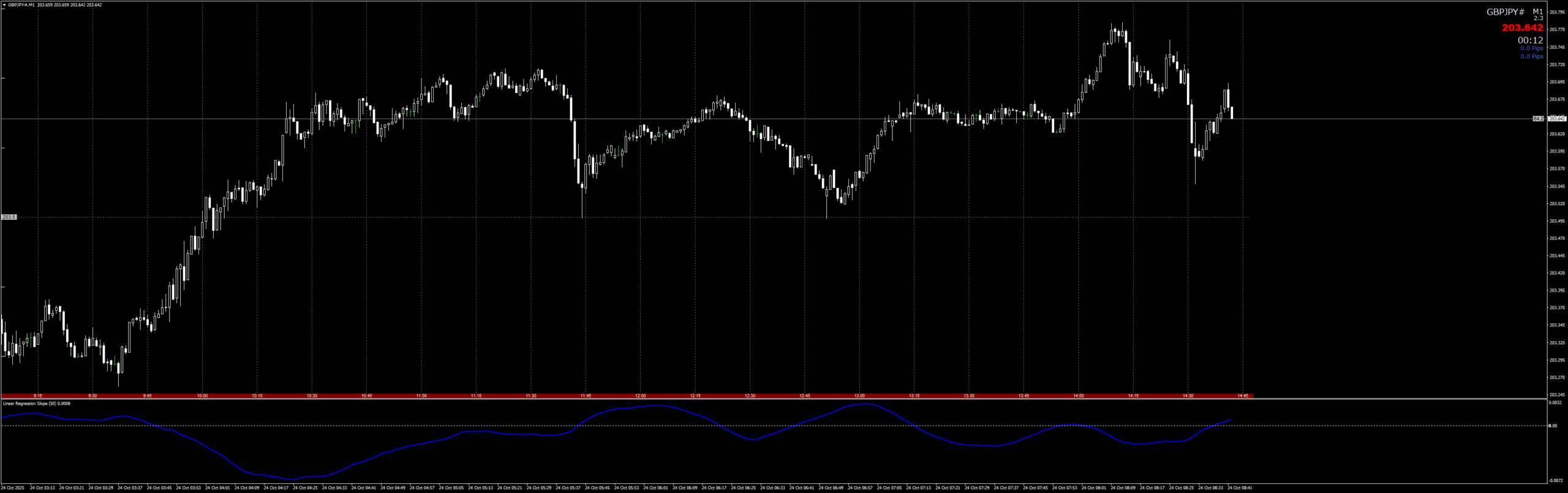
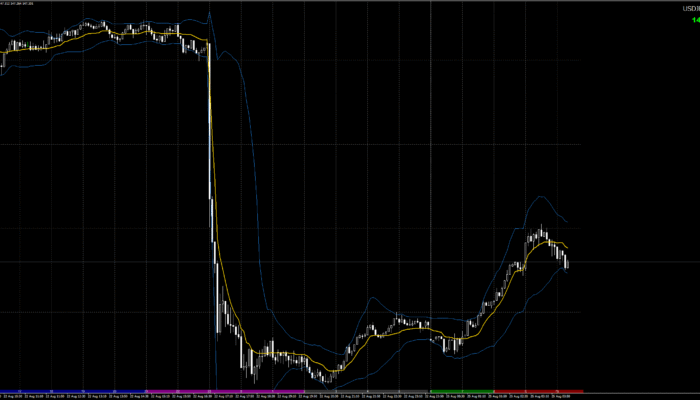


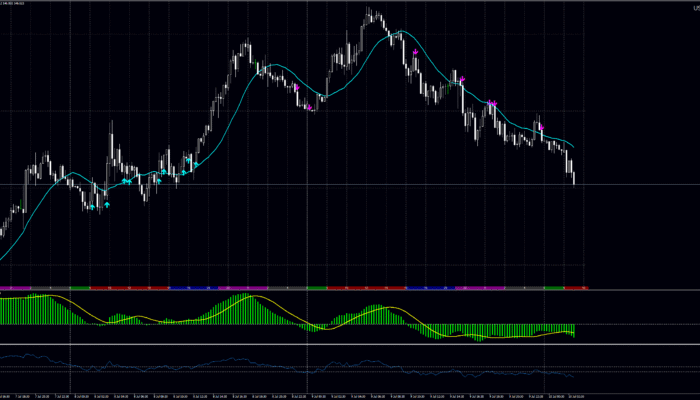
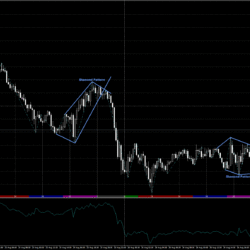
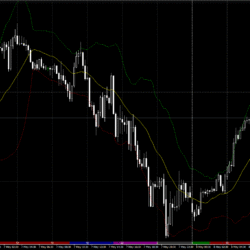

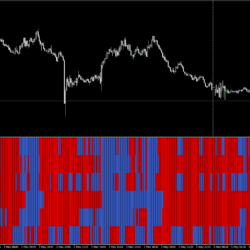
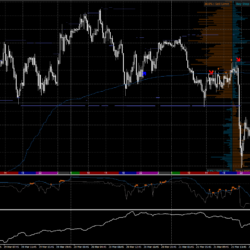

コメント